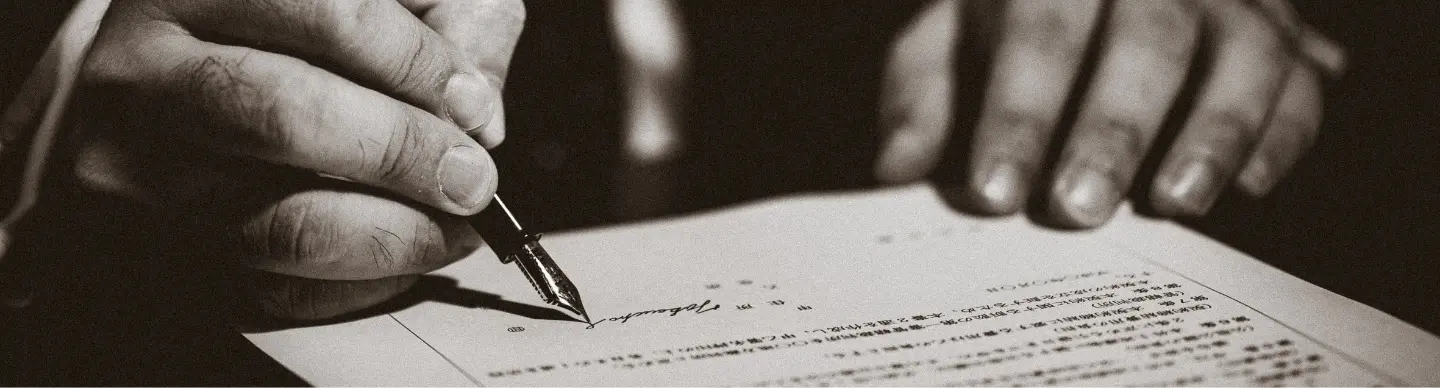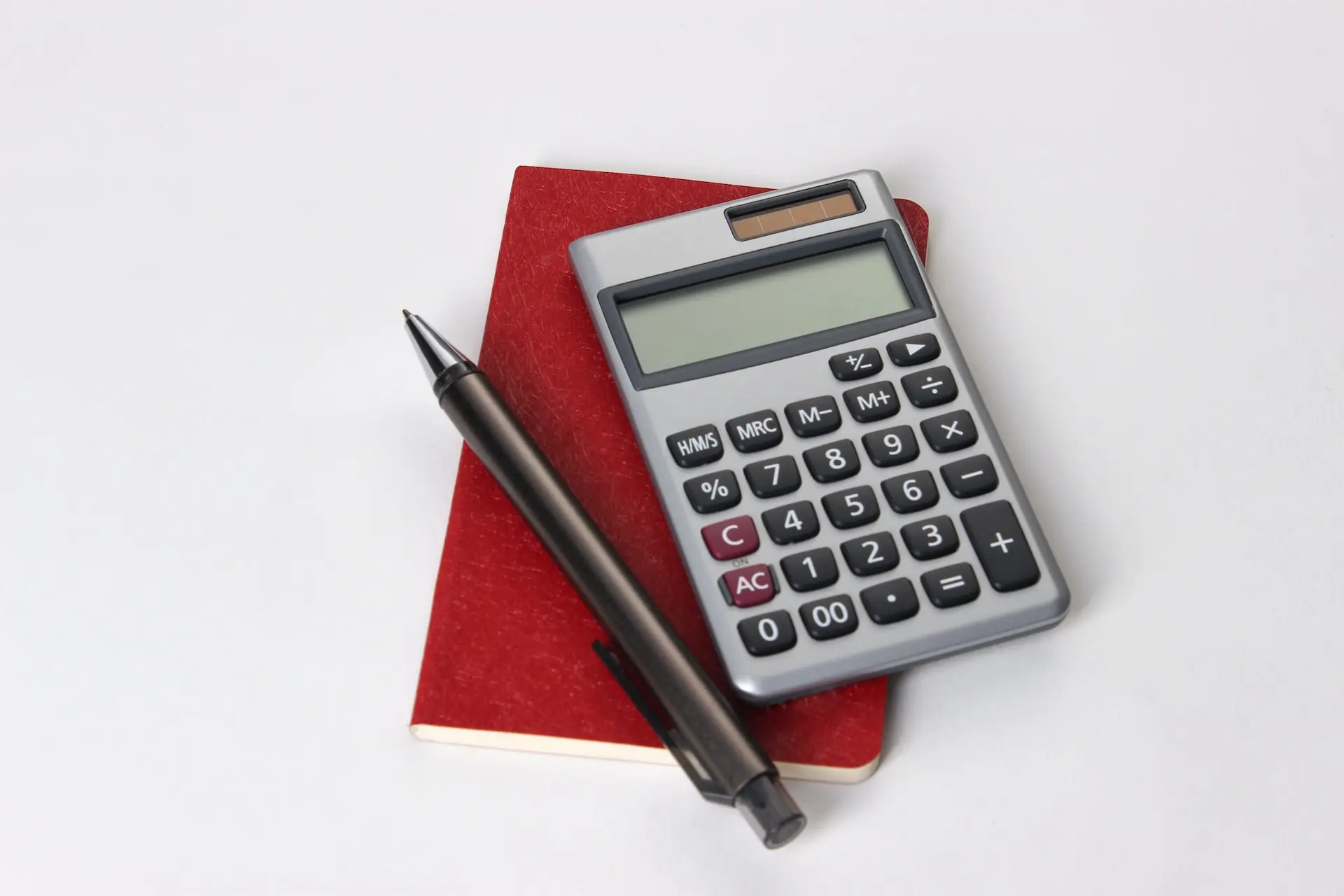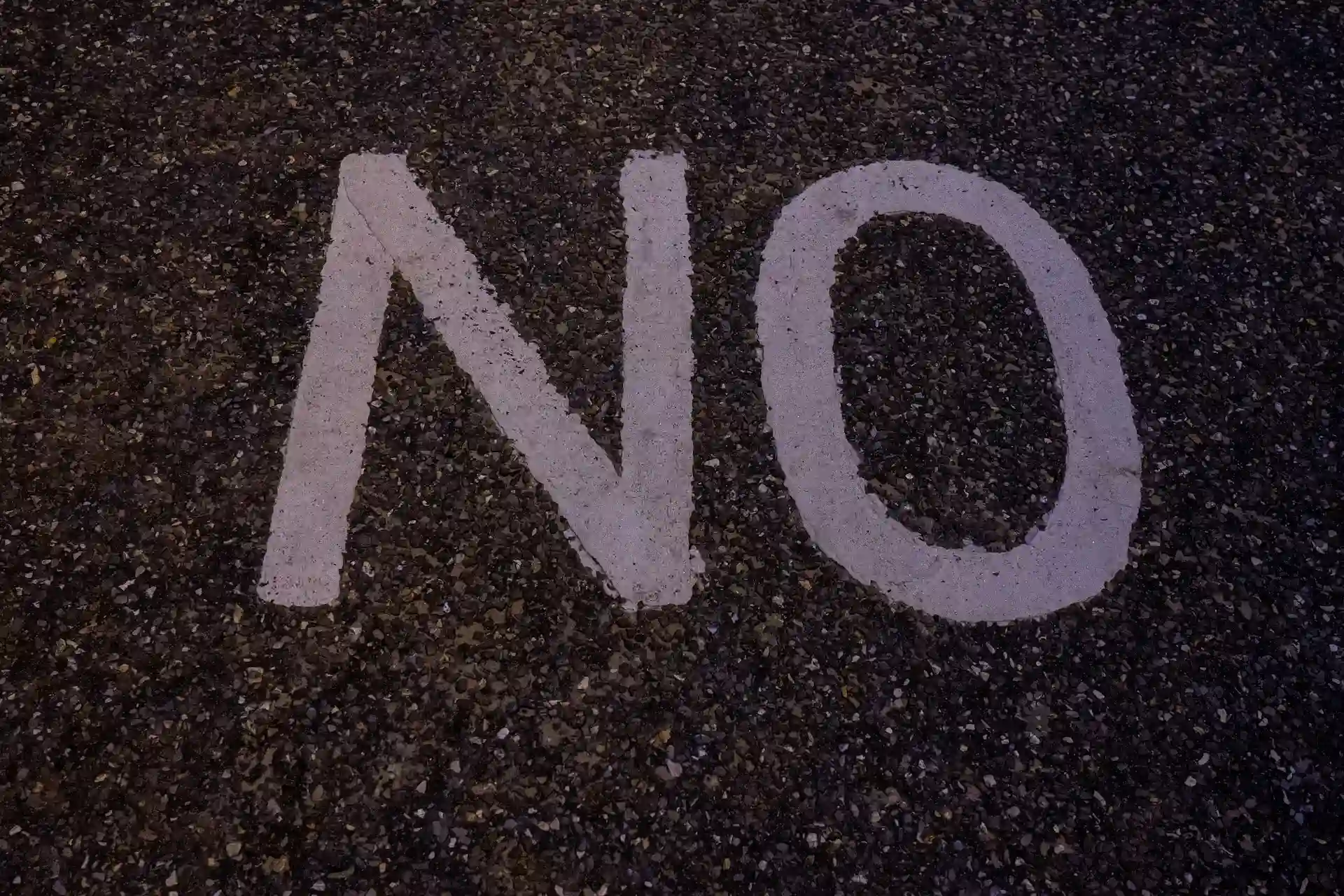Q.発達特性のある生徒Aは、クラス内で暴れたり、突然奇声を上げたりします。異性の生徒にかまわず抱きついたり、他の生徒と日常的にトラブルが起き、自分の子と同じクラスにしないでほしいという他の生徒の保護者からのクレームが後を絶ちません。オンラインでの参加を強制しようと思っていますが問題がありますか。
A.Aさんの特性を受け止め、原因を考え、周囲との軋轢を緩和する対話の機会を探りましょう。それでも改善しなかったり、自傷他害が想定される場合、強引な手法が許容されることもあります。
◎まずは配慮をしてあげましょう
質問のように、クレームがなされた場合、すぐにAさんをオンライン授業に行くように、強制させることには賛成できません。
やはり、まずは、Aさんはどうしてトラブルを起こしてしまうのかを探究することが必要です。発達障害をお持ちの生徒さんの場合でも、なぜトラブルになってしまうのかは生徒さんによって様々です。例えば、ある生徒さんは、「音」に過敏に反応してしまい、それでイライラしてしまうことがあります。また、隣の生徒と仲良くなりたいのだけれど表現方法がわからないために、すぐに抱きついてしまったり、トラブルが起こる理由は千差万別です。
まずは学校側としては、Aさんがなぜ抱きついたり、暴れたりするのか、その原因や背景事情を丁寧に聞き取るべきです。親御さんと話し合い、気持ちや事情に寄り添うべきです。Aさんからもきちんと話を聞いてあげることが必要です。他にも、スクールカウンセラーにア
ドバイスを求めたり、各自治体に存在する教育相談を利用して、良策を模索することが考えられるでしょう。
また、他の親御さんからクレームが来ているとしても、他の生徒や(他の生徒の)親御さんに対して、Aさんの特性を説明することも考えられるかもしれません。ただ、Aさんの特性はそれ自体、とてもセンシティブな情報ですので、AさんやAさんの親御さんが他の方に聞
かれたくないという意向を持っていた場合には、軽々にAさんの特性を話すことは許されません。話しても問題がないと考えられる場合に、他の生徒や親御さんと話し合うことで、Aさんが快適に過ごしやすくなる環境づくりに寄与することになります。また、他の生徒さんにとっても、他者の理解を促すことになったり、自分の振舞いを顧みたりすることにもなります。
このような取り組みを続けることで、Aさんを含むすべての生徒にとって、ベターな環境づくりを行っていきたいものです。
◎配慮を行うことは法律に決まっているのですか?
とはいえ、いつも万全な体制で配慮することはできません。法律では、どのような配慮を行うことが求められているのでしょうか。
2016年4月に障害者差別解消法という法律が施行されました。その法律の7条2項には、学校は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害及び高次脳機能障害も含む)を有する生徒から申出があった場合に「合理的な配慮」をしなければならないと規定してあります。以
前は私立学校の場合には、努力義務でしたが、昨今の法改正により、現在は公立学校も私立学校もこの法律を守らなければなりません。なお、障害者であるかどうかは,その生徒の状況等に応じて個別に判断されることとなり、いわゆる障害者手帳の所持者に限られないことも要注意です。このように、発達障害を持っている生徒から、SOSの申し出を受け取った場合、その生徒が快適に過ごせるように配慮を行う必要があるのです。
◎どんな配慮を行う必要があるのでしょうか?
2024年1月17日に文部科学省が「文部科学省所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針について」という通知を出しています。そこでは、合理的配慮の具体例について説明しています。
合理的な配慮は、ソフト面、ハード面など、あらゆる場面において、配慮をすることが求められます。ただし、あまりにも過重な負担が生ずる場合には、合理的配慮は要求されないと規定されています。
上記の通知では、例えば、下記の例が紹介されています。発達特性のある生徒さんは本当に千差万別ですから、その生徒にベターな方法が、別の生徒に当てはまるとは限りません。生徒ごとに、試行錯誤して試してみてください。
- 言葉だけを聞いて理解することや言葉だけでの意思疎通に困難がある障害者に対し、絵や写真カード、コミュニケーションボード、タブレット端末等のICT機器の活用、視覚的に伝えるための情報の文字化、質問内容を「はい」または「いいえ」で端的に答えられるようにすることなどにより意思を確認したり、本人の自己選択・自己決定を支援したりすること。
- 学校生活全般において、対人関係の形成に困難があったり、意思を伝えることに時間を要したりする児童生徒等に対し、活動時間を十分に確保したり障害の特性に応じて個別に対応したりすること。
◎配慮はどこまで必要なのでしょうか
もっとも、いつでも、つねに配慮を行うことが求められるわけではありません。障害者差別解消法7条2項では「実施に伴う負担が過重でないとき」に配慮を行うことが求められています。
どのような場合が「過重」にあたるかは一概にはわかりません。すぐれて個別判断と言えるでしょう。上記でも指摘した「対応指針」には過重かどうかを判断する要素としては、①事務・事業活動への影響の程度、②実現可能性の程度、③費用・負担の程度、④事務・事業規模、⑤財政・財務状況などが考えられるとしています。
ですから、学校の事業規模に比べて、高額な予算措置が必要な場合には、「負担が過重」と判断される可能性が高いでしょう。
◎ご質問の回答
Aさんがいわゆる法律にいう「障害者」であるかどうかはご質問からは明らかではないので、法律が確実に適用される場合か明らかではありませんが、それでも学校は、障害者差別解消法に沿った対応をすることが望ましいとは言えます。そのため、例えば、Aさんの席を変えたり、興奮する授業では別の課題を課すなど、ちょっとした工夫でAさんの問題行動が無くなる可能性もあります。
一方で、学校側は、他の生徒を保護することも必要であり、Aさんが誰かれかまわず抱きついてしまうというのは、いわゆる問題行動であって、ときとして法律に触れることもあります。また、考えられる方策を試したものの、あまり効果的でない場合や、そもそも、Aさんの問題行動の中身が、他の生徒さんを傷つけたりするような場合には、代替案を検討している余裕もないという場合もあるかもしれません。その場合には、ご質問のような対応を行うことも許容される可能性があります。
いずれにせよ、合理的配慮に正解はありませんが、質問のように、「他の生徒に対して迷惑をかけるであろう」といった漠然とした理由でオンライン授業を強制するのは問題があると思います。Aさんの特性を受け止め、トラブルになる原因を考え、周囲との軋轢を緩和する対話の機会を探りましょう。そのような対話を行ってもなお改善につながらなかったり、自傷他害など具体的な権利義務が侵害され、切迫している事情があるような場合には、ときとして強引な手法が許される場合もあると考えられます。
この記事の内容は、『学校運営の法務Q&A』(旬報社)をもとにお届けしました。教育現場のトラブル回避や法的対応をサポートする信頼の一冊。全国の書店やオンラインストアでお求めいただけます!
こちらからもお買い求めいただけます。