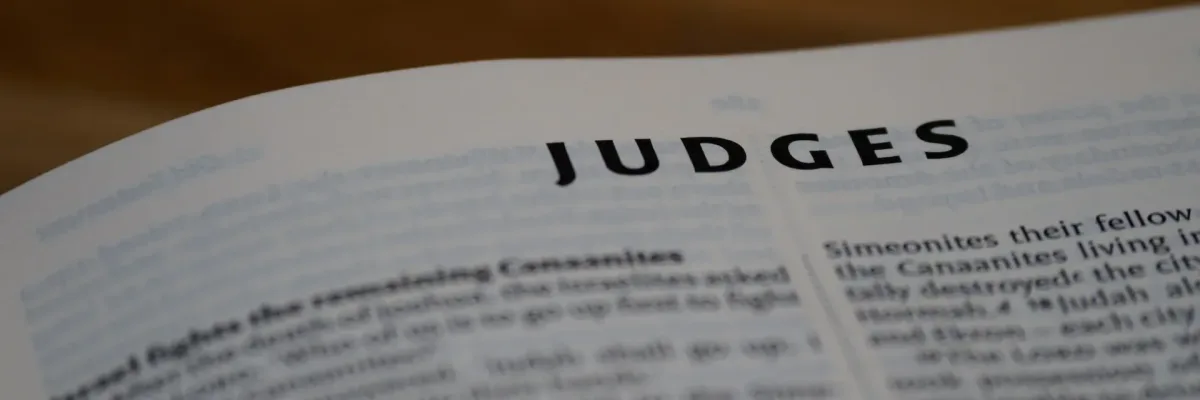私たちは自由に行きたい場所に行き、好きなものを食べ、好きな人と会話をすることができます。少なくとも、現代の日本ではこれが日常の風景です。しかし、逮捕や勾留は私たちからこの日常を奪います。警察署で寝泊まりを強要され、出されたものしか食べられず、家族との会話ができない状態になることは、一晩でも望ましくありません。しかし、驚くべきことに、日本の裁判官の一部はそうは思っていないようです。先日、私はそれを実感する経験をしました。
逮捕という言葉は、ニュースなどで頻繁に耳にするでしょう。実は逮捕によって人を拘束できる期間は最大で72時間と決まっています。捜査機関がそれ以上の身体拘束が必要だと判断した場合、裁判官に対して「勾留」というより長期の身体拘束を請求し、許可を得なければならないのです。
私たち弁護士の大切な役割の一つは、この段階で検察官や裁判官に働きかけて勾留を回避することです。多くの弁護士事務所がウェブページで「刑事事件はできるだけ早く弁護士に相談する必要があります」と述べているのは、そのためです。
もし勾留が決定してしまった場合、私たち弁護士は裁判所に対して「準抗告」を申し立てます。これは、勾留を決定したのとは別の三人の裁判官によって再考される制度です。東京地方裁判所には現在13の刑事部があり、そのうちのどこか一つに申し立てた準抗告事件が配転されます。準抗告が認められれば、勾留されている人は直ちに釈放され、家族の元へ帰ることができます。時間帯に関係なく深夜であっても釈放されます。
今回の驚くべき出来事は、この準抗告の場面で起きたのです。私のもとに勾留が決定したと裁判所から連絡があったのは平日午後2時ころでした。予め用意していた準抗告申立書を東京地方裁判所に提出したのは午後3時前ころでした。通常、配転された部の書記官から「うちの部が担当となりました。」という電話が入るので、それを待っていました。
すると、午後6時前頃、書記官から電話があり「準抗告を認めるか認めないかの判断は明日にすることになった。」と言われたのです。東京地方裁判所では準抗告を判断する担当の部が毎日順番で決まっています。夜であっても裁判官が待機する運用になっていたはずです。少なくともコロナ前はそうでした。それにも関わらず、もうその日は検討しないと言ってきたのです。
この時点でも異常に感じましたが、これで終わりではなく、次のようなやり取りが続きます。
「まだ午後6時です。なぜ今日判断しないのかの理由を説明して欲しいです。」
「裁判体(裁判官は裁判官3人で構成される判断者をこう呼びます)の判断だそうです。」「なぜそう判断したのか、その理由を聞いているのです。」
「裁判体の判断です。」
「埒が明かないですね。直接お聞きしますので裁判官に電話を代わって下さい。」
「少々お待ち下さい。…(保留)…裁判体の判断という以外話すことはないそうです。」「裁判官は人を拘束するということをどのように考えているんですかね。」
「…」
電話をかけているのは書記官であり裁判官ではありません。書記官は裁判官に指示されていることを伝えているだけです。それはわかっていましたが、あまりの対応の酷さに感情的になってしまいました。書記官の方には悪いことをしたと反省しています。
裁判官は早く帰りたかったのでしょうか。まさかそのような理由で人一人の身体拘束を一日伸ばしたりはしないと思いたいです。しかし理由を説明してくれないのでは邪推したくもなります。翌日にせざるを得ない理由があり、その判断が正しいと考えているのなら、なぜきちんと説明して理解してもらおうとしないのでしょうか。説明できなかったのは、自分たちの判断に対し後ろめたさを感じていたからではないのでしょうか。この裁判官三名は、取るに足らない理由によって、一人の人の身体拘束が延長されることを肯定したのです。
さらに驚くべきことに、この一週間後に別の事件で勾留決定に対する準抗告を申し立てた際にも同じ対応をされました。前回とは配転されたのが違う部であるにも関わらずです。東京地方裁判所ではこのような運用が常態化してしまっているのではないかと強い危機感を懐きました。
なお、準抗告に対する判断ですが、1件目は認められず勾留が継続し、2件目は認められ釈放になりました。しかし、「準抗告は認めるつもりがないから、今日の夜頑張って判断しても明日にしても結果は変わらない。」という考えも「明日釈放してあげるから一日ぐらい我慢しなよ。」という態度も、許されるはずがありません。
裁判官(の少なくとも一部)が身体拘束による身体的・精神的苦痛を軽視している実態が明らかになりました。このような運用を野放しにすれば、やがてそれが定着してしまいます。裁判官が無頓着に身体拘束を継続しないよう、強い姿勢で働きかけていかなければならないと強く感じる経験でした。