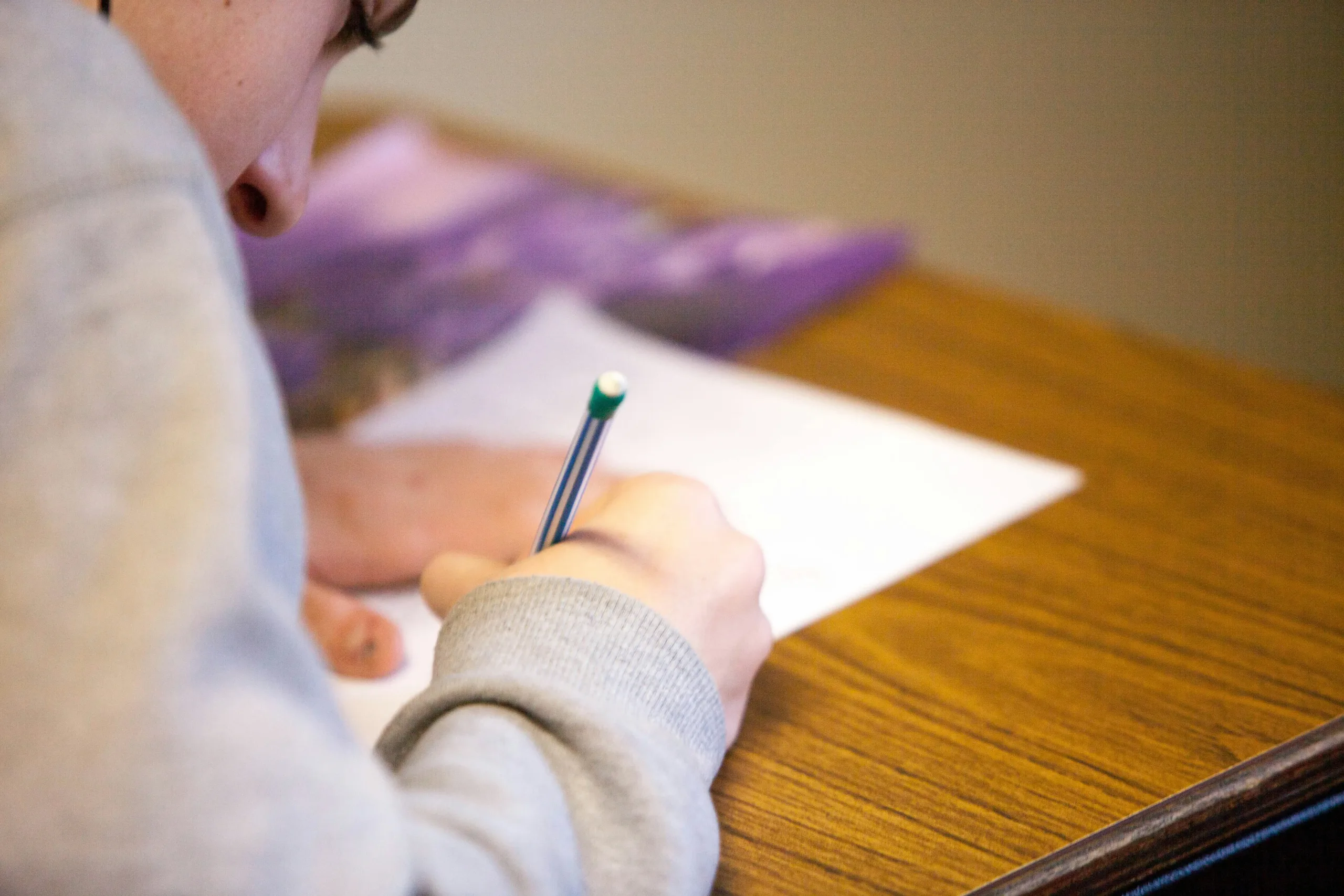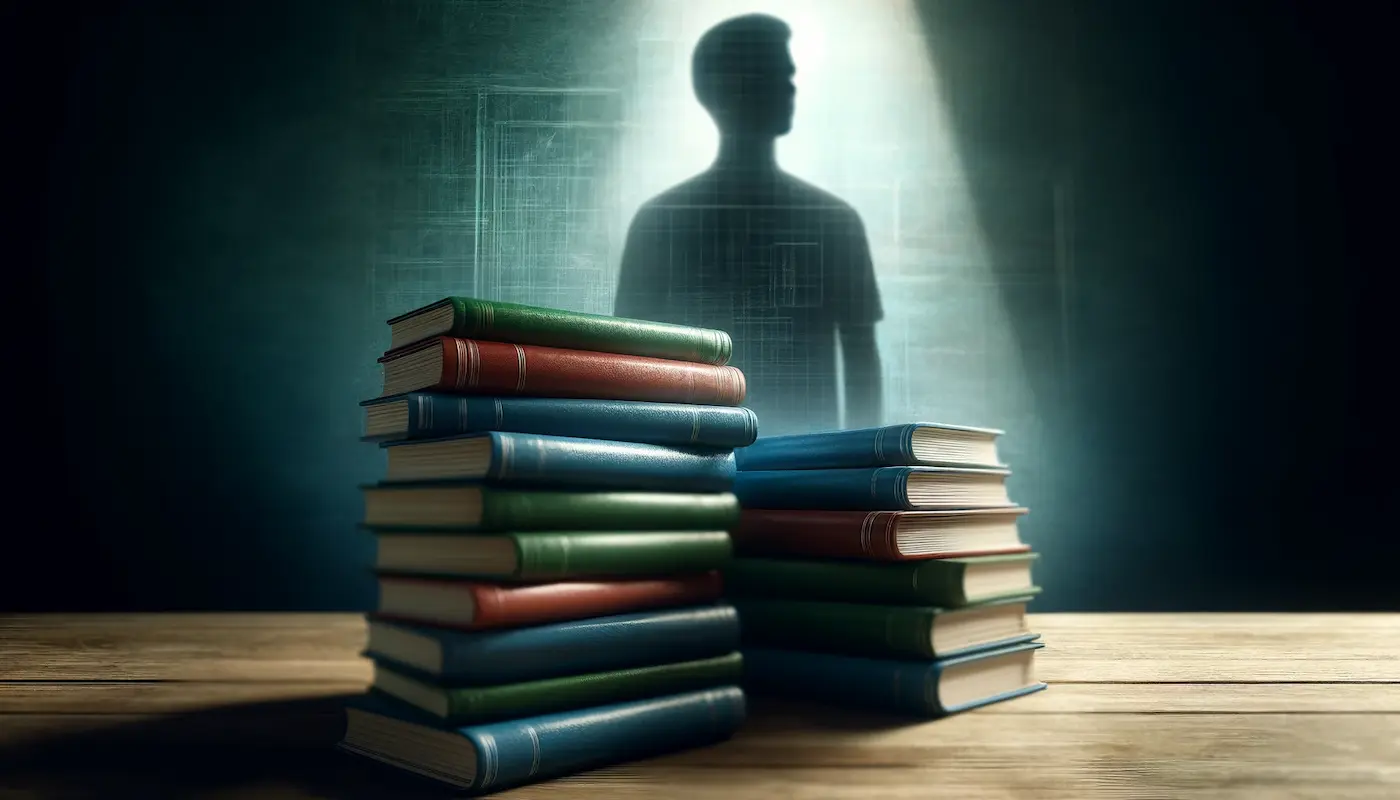Q.学校法人が教育方法の多様化のために大学以外の教育施設に授業の協力を求める際にどのような注意が必要でしょうか。
A.大学は、授業に主体的な責任を持ち、当該授業を教育施設に丸投げしてはなりません。大学は、教育施設と委託する業務内容について、詳細な協定書を作成し、教育施設の教育者に指揮命令を行わないようにしなければなりません。
◎教育内容の豊富化と授業での業務委託の利用
大学の教育内容の豊富化が求められる時代となっています。授業を担う大学教員についても、科目によっては、実務経験が重視されることも少なくありません。そして、例えば、会話を重視する語学教育などクラスの学生数を少人数として、ネイティブ・スピーカーを配置することにより、教育効果が上がる授業も増えています。しかし、この場合、到底従来の教員組織によって担うことはできないので、このような教育者を提供できる教育施設の協力を得る必要があります。
文科省も授業科目について、「全てを当該大学のみで行うことを求めるものではなく、教育内容の豊富化等の観点から、大学が当該大学以外の教育施設等と連携協力して授業を実施することも認められる」(19文科高第281号平成19年7月31日)としています。
◎大学以外の教育施設を利用する場合に注意しなければならないこと
文科省によれば、大学以外の教育施設を利用する場合について、以下のような実施条件を示しています。
まず、大学と教育施設との間の協定書(契約)において、①授業の内容、方法、実施計画、成績評価基準及び当該教育施設等との役割分担等の必要な事項を定めておくことです。次に②大学の授業担当教員の各授業時間ごとの指導計画の下に実施されていることです。さらに、③大学の授業担当教員が当該授業の実施状況を十分に把握していること、加えて④大学の授業担当教員による成績評価が行われることです。
このように、大学以外の教育施設を利用するとしても、大学自体が主体的に責任を持って、当該大学の授業として適切に位置付けて行われることが求められていることに十分注意が必要です。つまり、教育施設への丸投げは認められないということです。
◎偽装請負と評価されないように注意しなければならない
文科省は、上記したように、実施条件を詳細に協定書に定めることを求めています。これは、業務委託契約における仕様書に当たると考える必要があります。というのは、大学の責任を持った関与は必要ですが、それが、教育施設に雇われている教育者に対する指揮命令と
評価されるような形態であると、労働者派遣法の観点からは実質的には労働者派遣となり、同法に違反する偽装請負と評価される危険性を孕むことに十分注意が必要です。教育施設の教育者に委任している内容が協定書に詳細に定められており、大学が当該教育者の教育に対する具体的な指揮命令を行う必要のないようにしておかねばなりません。
このことは、協定書に定めるだけではなく、教育施設に教育者に周知するよう求めるとともに、授業科目の責任教員に十分に周知しておかねばなりません。そして、当該教育者の指導に問題があると判断した場合の対処法についても、あらかじめ徹底しておく必要があります。
なお、教育施設の教育者の職名名称は、「非常勤講師」のような学校教育法上授業担当教員となることができる者と誤解されるような名称を使わないことにも注意しましょう。
この記事の内容は、『学校運営の法務Q&A』(旬報社)をもとにお届けしました。教育現場のトラブル回避や法的対応をサポートする信頼の一冊。全国の書店やオンラインストアでお求めいただけます!
こちらからもお買い求めいただけます。