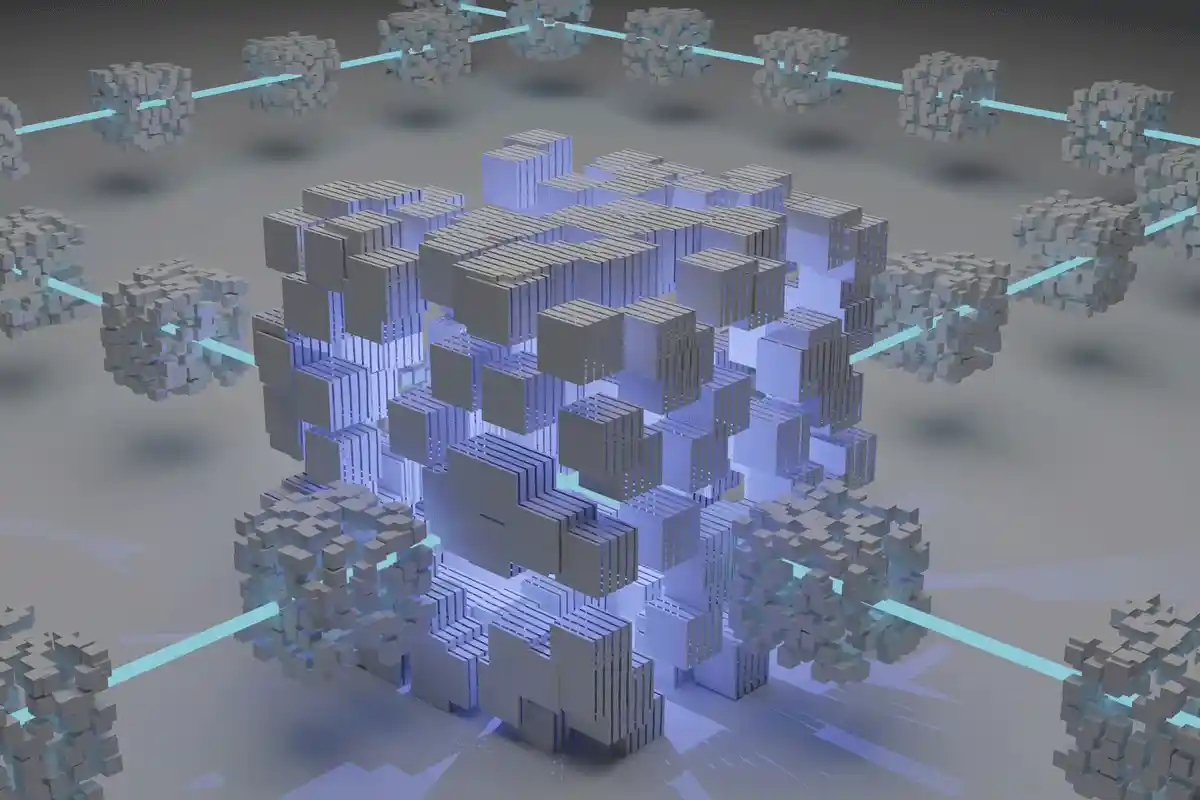河﨑健一郎です。
このところの生成AIの発展で、仕事をするにもAIは欠かせないツールになってきていますね。
そんななか、今日飛び込んできたのがGoogleのNotebook LMというツールのPodcast機能が、日本語対応したというニュース。Notebook LMとか、Podcast機能とかなんじゃろそれ、という方もおられるかも知れませんが、百聞は一見(一聴)にしかず、ということで、こちらの音声をどうぞ。7分ほどの「ラジオ番組」です。
一部の固有名詞に誤った発音などはあるものの、取り上げられている内容には概ね間違いはありません。なによりとても流暢なやりとりで、本当にラジオパーソナリティの男女が当事務所について調べたうえで、紹介してくれている番組なのではないか、と錯覚してしまいます。
実のところこれは生成AIが作成した音声データで、当事務所のリサーチャーがNotebook LMの機能を用いて「チャチャっと」作り上げたものです。作成時間は3分とのこと。いやはや、すごい時代になったものです。
AIが描く姿と実像のギャップ
ところで本稿の目的は、上のPodcastを紹介することではありません。上のPodcastに私が感じた些細な違和感、それについて書きたいと思います。
私が感じた些細な違和感、それは、「確かに内容に間違いはないんだけど、強調すべきポイントが微妙にズレているんだよなあ」というものです。
たしかに当事務所は学校法務センターを設立し、その活動に力を入れたり、Web3.0関係の法的支援を取り扱っています。しかし、当事務所の扱っている案件の一番の「ボリュームゾーン」は、企業法務であれば一般の企業の日々の活動を支えるジェネラル・コーポレートと呼ばれる部分だし、市民法務であれば日々の生活で生じる種々雑多な紛争の解決なのです。
フォーカスするポイントの微妙なズレが、当事者として感じた些細な違和感につながっているのだと感じました。
なぜズレが生じるのか
で、なぜそのようなことが起こるのか、というと、生成AIは言語化されて表明されている情報に基づいてコンテンツを生成するからにほかなりません。
一方で私達は、あたりまえに取り組んでいることは「当たり前」すぎて、わざわざ事務所のウェブサイトで表現したりしません。
しかしその部分の言語化と表明を怠っていると、当事務所についての「AIの要約」が、「間違ってはいないけれど、少しズレたもの」になってしまう危険性があるということに、このPodcastを通じて改めて気付かされました。
というわけで、これから数回に渡って、現在のわたしたちの事務所がどんな事務所で、どんな業務を扱っていて、どんな将来を見据えているのか、文章化して書き綴ってみたいと思います。