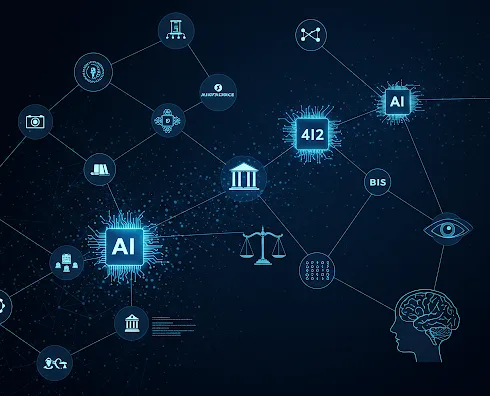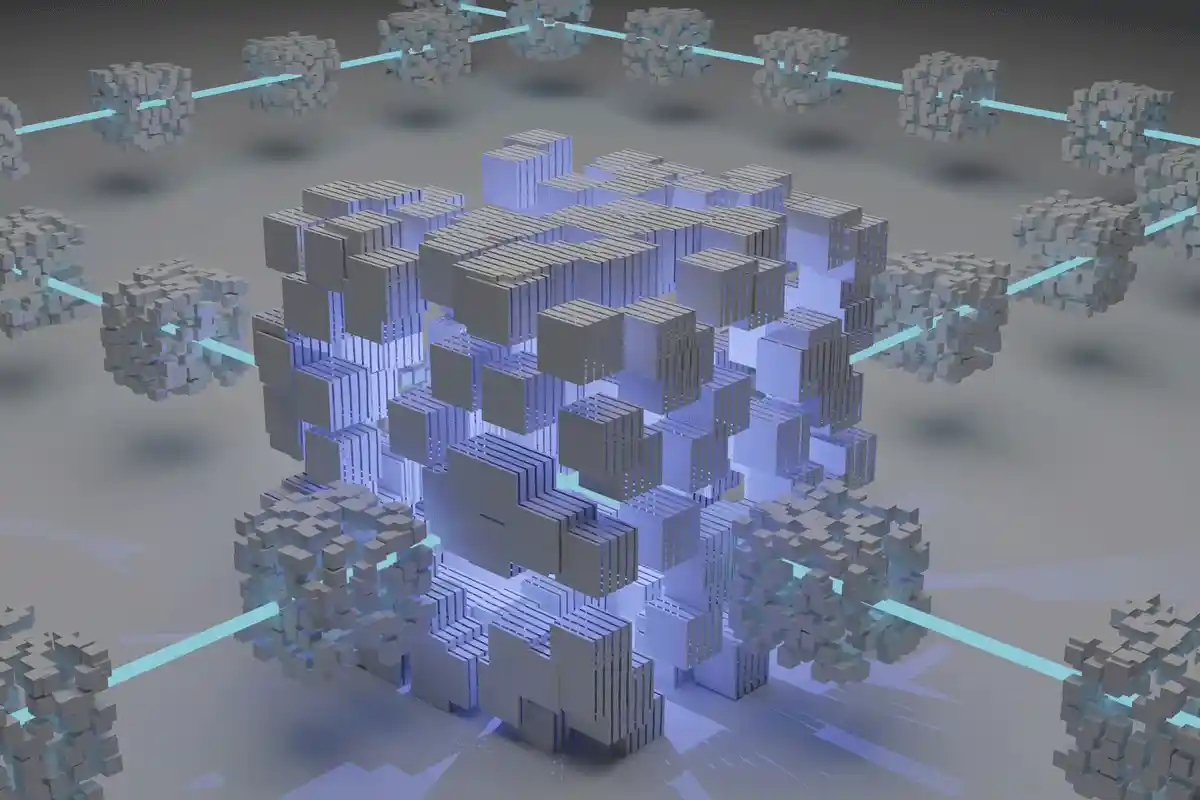Q.少子化で生徒が思うように集まらず、学校経営を続けていくことに困難を感じています。学校を廃止や縮小する場合にはどのような手続きが必要でしょうか。
A.学校法人の廃止・縮小に際しては、行政の認可が必要であるほか、学生と保護者、地域、教職員、地域社会それぞれと、丁寧にコミュニケーションを行いながら進める必要があります。
◎行政との調整
学校の廃止や学校種の変更を行う場合、原則として、学校教育法4 条に基づき、文部科学大臣の認可が必要となります。この認可申請には、廃止理由書、在学生の処置計画、教職員の処遇計画、財産処分計画などの詳細な資料の提出が求められます。認可申請の準備にはかなりの時間と労力がかかり、認可が得られるまでには認められるかどうか不安定な状態が続きます。学校の廃止等を検討される場合は、早期からの計画立案と文部科学省との事前相談が不可欠です。また、私立学校等経常費助成金や施設設備費補助金などを受けている場合、学校の廃止や用途変更により、補助金の返還を求められる可能性があります。この点に対しては、補助金適正化法等の関連法規の十分な理解と、文部科学省等との早期段階からの協議が重要です。場合によっては、段階的な縮小計画の策定による返還額の最小化や、他の教育事業への転用といった代替案の提案も検討する必要があります。
◎学生・保護者への対応
学校の廃止・縮小は、在学生の学習機会に直接的な影響を与えます。
十分な周知期間の確保(最低でも1 年以上前からの通知が望ましい)と、個別面談の実施等による丁寧な説明が重要です。近隣校との連携による転学先の確保や、転学に伴う経済的支援(転学先への入学金補助など)の検討が必要となる場合もあるでしょう。また、入学試験合格者や入学手続き済みの生徒がいる場合は、早期の情報開示と丁寧な説明、入学金の一部、または全額の返還、代替の進学先の紹介と手続き支援などの対応が必要となる場合があります。
◎地域社会への配慮
学校の廃止は、地域社会に大きな影響を与えます。地域の教育機会の喪失や地域経済への悪影響、地域住民からの反発などに対応するためには、早期からの情報開示と地域住民との対話が重要です。場合によっては、地域自治体との連携や、学校施設の地域貢献施設への転用(図書館、生涯学習センターなど)を検討することも一案です。
学校廃止にともない、学校法人が保有する資産(土地、建物など)の処分が必要となる場合もあります。この際には、適正評価と売却計画の策定、地域のニーズに合った跡地利用計画の提案が重要となります。なお、資産処分にあたっては文部科学省との協議による寄附行為の変更も必要になる場合があります。
◎実務的な対応と留意点
学校の廃止・縮小プロセスにおいて、適切な情報開示とコミュニケーションが極めて重要です。ステークホルダー別の説明会の開催や専用の相談窓口の設置、定期的な進捗報告など詳細なコミュニケーションプランを立てたうえで臨むことが求められます。教職員の処理についても問題になりますが、別項目(Q1 〜 3)で詳述していますので参照ください。
なお、学校の廃止後も、学校教育法施行規則第28条第2 項に基づいて各種記録の5年間の適切な保存と管理が義務付けられている点については留意が必要です。
この記事の内容は、『学校運営の法務Q&A』(旬報社)をもとにお届けしました。教育現場のトラブル回避や法的対応をサポートする信頼の一冊。全国の書店やオンラインストアでお求めいただけます!
こちらからもお買い求めいただけます。