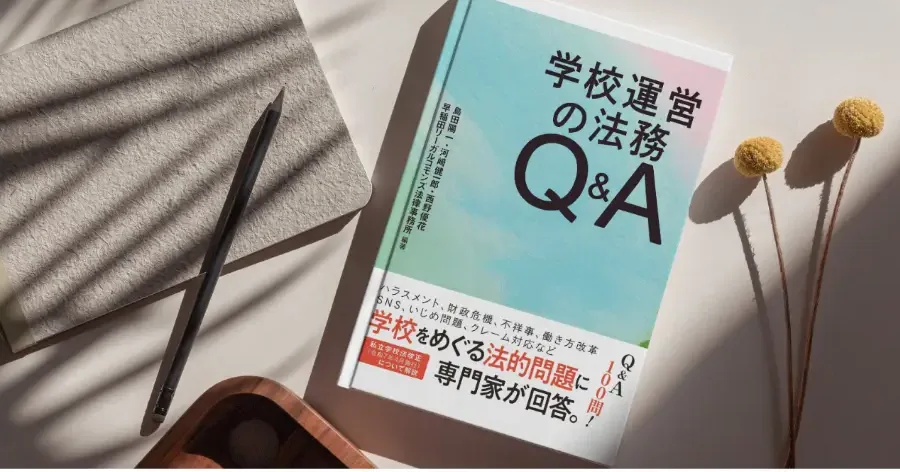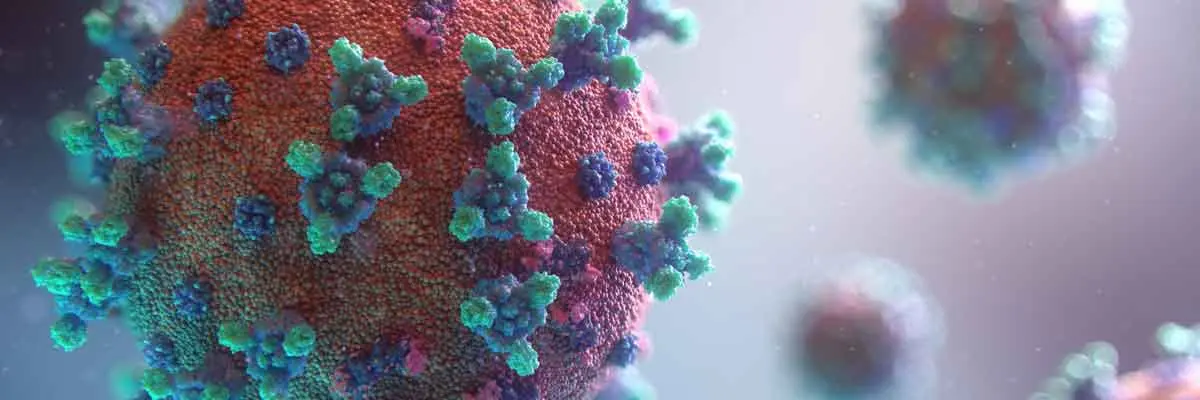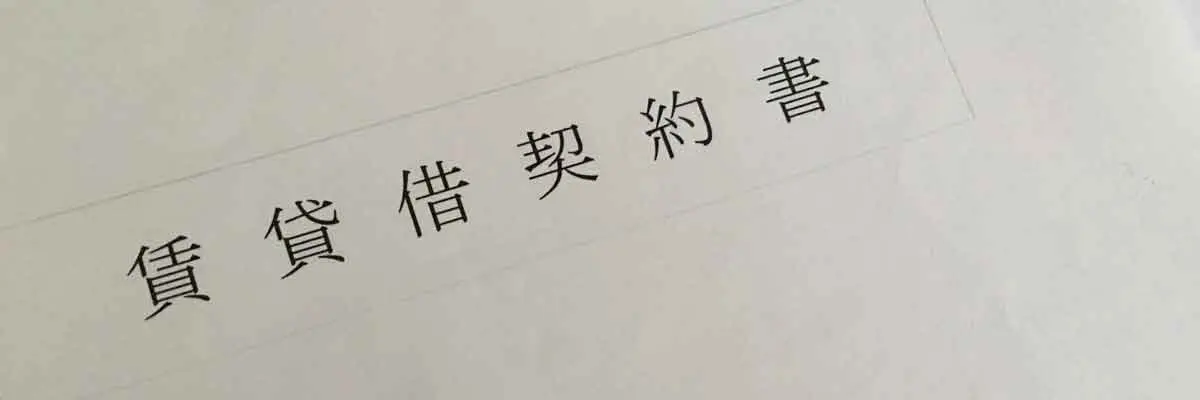1.遺言の限界
遺言とは、自ら築いた財産を、死後、その意思に従って遺された人に分配するための制度です。ところが、遺言の内容は、必ずしもそのまま実現されるとは限りません。以下の事例を見ながら、遺言からどのようなトラブルが生じるか、検討してみましょう。
(1)登場人物
今回遺言を作成するのは、80代の男性A。Aには妻がいましたが、既に先立たれていますので、法定相続人は、50代の子である長男Bと、次男Cの2人のみです。
(2)遺言者Aの考え
Aは、自分がこれまでに働いて築いた財産を、自分の子であるBとCのうち、より自分の家計を助けてくれ、また、自分の生活を支えてくれた者に譲ろうと考えました。
経済面では、Bは高校卒業後すぐに家を出て独立して働き始めたため、Aに学費や生活費の負担もさほどかけていませんでした。一方、Cは、Aに大学の学費負担をさせた上、社会人になってからも何かとAに金銭的な援助をしてもらっていました。
また、生活面では、Bは、Aが妻に先立たれ、段々と体調も悪くなっていった時、わざわざAの近くに引っ越して一人で暮らすAの家事を手伝ってくれました。一方、Cは遠くに住んだまま、Aにあまり連絡もよこしませんでした。
このような事実を踏まえて、Aは、自分が亡くなった後、これまで金銭的な負担もかけず、家事を手伝うなどしてくれたBに残った財産を全て譲ろうと考え、その内容の公正証書遺言を作成し、自分が亡くなった後に備えたのです。その後程なくして、Aは死亡しました。
(3)法定相続人Cの考え
ここで、Cに視点を移してみましょう。Cは、Aが亡くなった後、遺言が残されていることを知り、その内容を見ました。そこには、「相続財産は全てBに相続させる」という言葉があるのみでした。何故自分は相続を受けられないのか、その理由について知ることができません。Aの遺言に納得できなかったCは、「BがAの自宅の近くに住み、家事を手伝うために週に数度、Aの家に出入りしていた。ひょっとしたら、Bは日頃からAに何か吹き込んでいたのかもしれない。」などと考え、Bに対して遺言の内容について不服を述べますが、Bはこれに取り合いませんでした。
ところで、民法は遺留分侵害額請求(民法の改正前は「遺留分減殺請求」と呼ばれていました)という制度を設け、相続を受けられなかった法定相続人(ただし亡くなった人の兄弟、姉妹を除く)は、その法定相続分(この事例でいうと、BとCが2分の1ずつ)の半分までは、その取り戻しを請求することができます。
Cは、遺言の内容に不服があったことから、この遺留分侵害額請求をすることとしました(今回でいえば、相続財産全体のうち4分の1までの財産をBから取り戻すことができます)。
その後、結局、CとBの争いは、調停を経てもまとまらず、最終的に遺留分侵害額請求訴訟にまで発展することとなりました。
2.遺言の内容から生じた訴訟
Cが遺留分侵害額請求をした場合、遺言を通じて残されたAの遺志は、残念ながら100パーセントは尊重されないことになります。さて、このように兄弟間での争いが訴訟にまで至ってしまったことの原因は、どこにあるのでしょうか。
ひょっとすると、その原因は遺言の内容そのものではなく、CがAから「きちんと説明を受けることが出来なかった」ことにあるのかもしれません。共に過ごした時間が長い分、家族の問題は多分に感情が入り込みます。感情の部分で納得できれば、訴訟という形で争いが顕在化することもなかったかもしれません。
3.付言事項って?
上記のような訴訟トラブルを避けるための方法として、遺言に「付言事項」を記載することが考えられます。今回は、この「付言事項」とは何かについてご説明します。
まず、遺言の内容には、大きく分けて「法定遺言事項」と、「付言事項」があります。
前者の「法定遺言事項」は、遺言に記載することによって法的な効力を生じる事項を言います。例えば、相続財産の何を誰に譲るかといった内容(相続分の指定)などが挙げられます。一方、後者の「付言事項」は、「法定遺言事項」以外の事項、すなわち法的な効果を持たない内容を指します。
この「付言事項」は、法的な効力を持たない分、自由にその内容を記載することができます。最もよくされるのは、何故そのような内容の遺言となっているかの理由を記載した、遺言者の相続人へのメッセージです。遺言者が何を考え、残された家族にどう過ごして欲しいのかを記載することによって、家族への想いを残すことができるのです。
遺言書での具体的な書き方としては、遺言書の最初の部分に法定遺言事項を書き、その後ろに「付言事項」とタイトルをつけて付言事項を記載する例が多いです。1点注意してほしいのは、法定遺言事項か、付言事項かは、タイトルではなく内容で決まります。ですので、付言事項というタイトルをつけていても、そこに記載された内容が法定遺言事項であった場合には、それは法定遺言事項として取り扱われます。
今回の事例では、Cはひょっとしたら、他ならぬAから、何故CではなくBに財産を相続させるのかの説明を受け取れば、自分がAの財産を相続できない理由に納得し、Bに不服を述べることはなかったかもしれません。また、自分の親であるAから「BとCは、兄弟として仲良く過ごして欲しい」といったメッセージを受け取れば、兄であるBに対し、訴訟など提起することもなかったかもしれません。その意味で、法的にはともかく、付言事項には事実上の価値があると言えるでしょう。
遺言の内容のうち、付言事項は法的な意味を持つものではありません。しかし、多数の相続トラブルを目の当たりにしてきた弊所の弁護士は、このような事実上の効果も踏まえ、適切な内容の遺言を作成できるようアドバイスすることができます。さらに、弊所では映像で遺言者のメッセージを残す映像遺言サービスも行っています。大切な家族だからこそ、気持ちの部分もしっかり残すことをおすすめします。