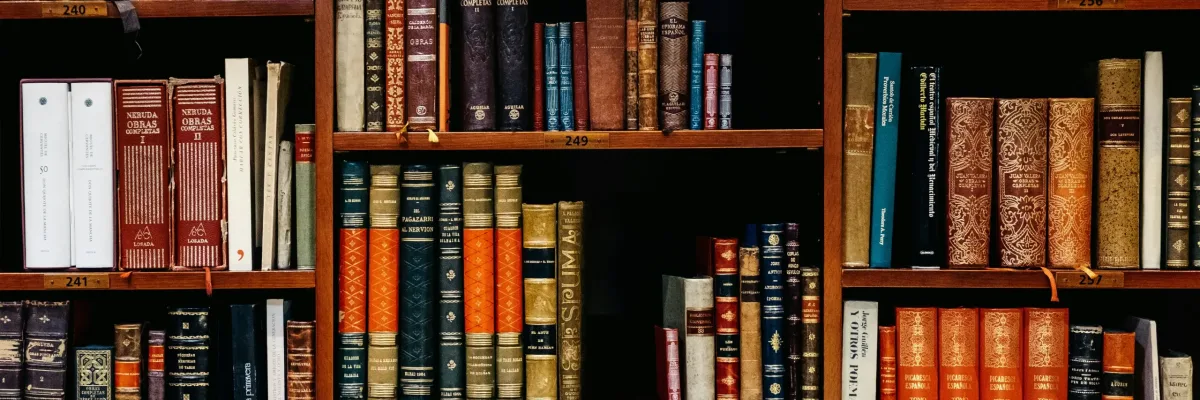Q.生徒の保護者から、子どもが学校でいじめに遭っている、以前から担任の先生に相談しているのに全く対応してくれない、学校は調査をする義務があるはずだと言われています。どうしたらいいでしょうか。
A.まずは事実確認を行いましょう。生徒や保護者から「いじめにより重大な被害が生じた」との申立てがあればいじめ重大事態調査が必要です。
◎そもそも「いじめ」とは?
いじめ防止対策推進法(以下、「いじめ防止法」)は、「いじめ」を「当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」(同法2条1項)と定義しています。被害者側が体や心に苦しみ、痛み、つらさなどを感じた場合には「いじめ」にあたります。いじめは多人数で1人をいじめたり、物を壊されたり殴られたり、被害者が学校に来ることができなくなるような苛烈なものと考えられていることも多いように思いますが、法律上の定義では、1人対1人でも、より軽微と思われるものでも、いじめにあたりえます。法律では「いじめ」の対象を広く設定することで、何よりもまずは被害者の心身を保護して重大な事態を防ぎ、早期にいじめの芽を摘むことを目標としています。
本問でも、お子さんがいじめ被害を保護者に訴えて、保護者が担任や学校に相談したのかもしれません。ただし、こうした場面では、子ども自身の気持ちが置き去りにならないように気をつけましょう。
いじめに対しては様々な対応が必要となりますが、いじめ対応の出発点は子ども自身です。一方で、子ども自身は心配をかけたくない、大事にしたくないといった気持ちから、いじめ被害を否定する場合もあります。こうした際には、本人の様子を注意深く観察したり、周辺の他の生徒などから客観的な状況を確認したりすることも必要です(「いじめの防止等のための基本的な方針」文部科学大臣決定、平成29 年3月14 日最終改訂、4頁。以下、「いじめ防止法ガイドライン」)。
◎いじめが疑われる場合に、教員や学校はどうすべきか
いじめ防止法は、児童生徒からいじめの相談を受けた教員や保護者等に対して、「いじめの事実があると思われるとき」に学校への通報等をすることを求めています(同法23 条1項)。相談を受けた教員が「この程度ではいじめではない」と判断して一人で抱え込んだり相談を握りつぶしたりすることがないように注意しましょう。
保護者や教員から通報を受けた場合や、児童生徒がいじめを受けていると思われるときには、学校は以下の5つの義務を負います。
これら義務に関しては、いじめ防止法ガイドライン別紙2「学校に
②いじめをやめさせ、再発を防止するため、被害者とその保護者を支援し、加害者に指導し、加害者の保護者に助言することを継続的に行う義務(同条3項)
③被害者が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずる義務(同条4項)
④いじめに関する情報を被害者・加害者それぞれの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずる義務(同条5項)
⑤いじめが犯罪行為に該当しうるときは警察署と連携し、児童等の生命・身体・財産に重大な被害が生じおそれがあるときは警察署に通報し援助を求める義務(同条6項)
おける「いじめの防止」「早期発見」「いじめに対する措置」のポイント」も参考になります。
学校設置者も必要に応じて学校への支援や調査等を行う義務があり(同法24 条)、校長及び職員は加害者に対して教育上必要がある場合には懲戒を行うことができます(同法25 条、学校教育法11 条)。
本問で生徒がいじめ被害を訴えている場合、担任の先生は学校に対してこれを報告する必要がありましたし、学校は①の事実調査を行うことが必要でした。仮に生徒自身がいじめを否定したとしても、いじめの事実があると思われる場合には、報告や事実調査を行うことが必要です。いずれにせよ、本問において学校は、生徒自身の認識を確認し、クラスの状況等を確認することを出発点とするべきでしょう。
◎いじめ重大事態調査とは
以下のいずれかに該当する場合は、「重大事態」として速やかに学校の下に組織を設け、事実関係を確認するための調査を行うことが義務付けられています(同法28 条)。
ⅱ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき(不登校重大事態、28条2号)
さらに、「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」においては、児童等や保護者から、「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったときも重大事態が発生したものとして報告・調査等にあたるべきことを指摘しています(文部科学省、令和6年8月改訂版)14 頁。以下、「いじめ重大事態ガイドライン」)。したがって、以下の3つ目の場合も重大事態として扱うこととなります。
ここにいう調査を「いじめ重大事態調査」、組織を「いじめ重大事態調査委員会」と呼びます。委員会の構成についてはQ80、具体的な事例についてはQ81 をご参照ください。
本問についても、重大事態に該当するのであれば、上記事実調査にとどまらず、いじめ重大事態調査委員会を立ち上げていじめ重大事態調査を行う必要があります。この場合は保護者の申立てで調査を開始しなければならないことにも注意しましょう。
なお、ガイドラインでは必要に応じてまずは法23 条2項の学校いじめ対策組織による調査を実施する対応をとる場合も否定していません(いじめ重大事態ガイドライン14 ~ 15 頁)。判断に迷う場合には、専門家からの助言を得ることも検討しましょう(同13 頁)。
◎いじめを見逃したら?
いじめを見逃した場合、学校は法的責任を負うのでしょうか。
いじめにより被害者に損害が発生した場合(物が壊される、心身にダメージが負わされる等)、まずその責任を負うのは加害者側です。
ただし、学校も児童生徒の生命・身体・財産の安全に配慮するべき安全配慮義務を負い、その中にはいじめの被害をできる限り軽減する義務が含まれています。
学校がいじめを放置して適切な対応をとらず、それにより損害が発生したといえる場合、安全配慮義務違反により学校が損害賠償責任を負う可能性があります。
児童生徒や保護者からいじめの相談があった際には事実確認を行うことを徹底しましょう。本問のように教員が学校にいじめの報告をしないことが後で問題となることがないように、教員同士や教員と管理職が連携をとりやすい組織づくりをしておくことが重要です。
この記事の内容は、『学校運営の法務Q&A』(旬報社)をもとにお届けしました。教育現場のトラブル回避や法的対応をサポートする信頼の一冊。全国の書店やオンラインストアでお求めいただけます!
こちらからもお買い求めいただけます。