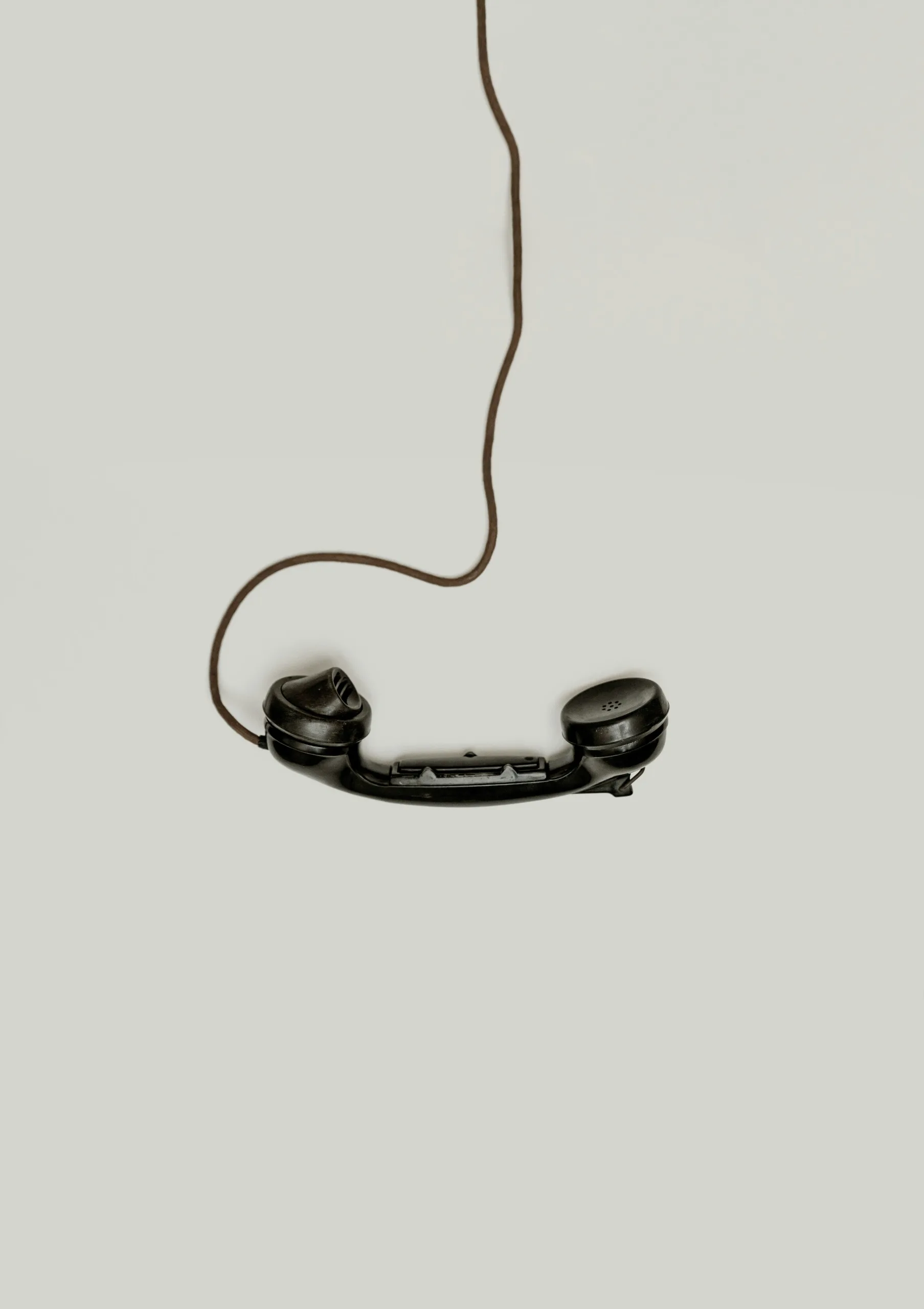Q.部活動のコーチがハラスメント行為を行っているとの訴えがありました。コーチは当校で雇用している方ではなく、OB がボランティアでやっているものです。
職員ではないため、懲戒しようがないようにも思えますが、どうしたらよいでしょうか。(私立・公立両方)
A.懲戒権の有無にかかわらず、生徒等の安全確保が必要です。事実調査のうえ、コーチによるハラスメント行為を認定した場合、今後の部活動への関与を禁止するなどの措置をとってください。
◎外部指導者によるハラスメント行為への対応
学校と直接雇用関係にない部活動の外部コーチであっても、生徒等に対するハラスメント行為が許されないことはいうまでもありません。
校長及び部活動の顧問教員には、部活動の実施に当たり、体罰やハラスメント行為の根絶を徹底することが求められています(2022(令和4)年12 月文部科学省・スポーツ庁「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」。以下「部活動ガイドライン」)。したがって、学校としては、外部指導者によるハラスメントの予防活動にとどまらず、外部指導者によるハラスメント行為を認知した場合には、適切に対処し、事実調査と再発防止策を講じることが求められます。
再発防止策としては、学校から部活動顧問に対し、ハラスメント行為に及んだ外部指導者への協力依頼の速やかな中止を指示するとともに、学校から当該外部指導者に対し、今後の部活動への関与(学校敷地内や部活動現場への立ち入りを含む)を禁止することなどが考えられます。
これとあわせて、部活動顧問に対し、当該指導者の関与のない状態で部活動を実施していることの報告を定期的に求めるなど、再発防止策の実効性を確保する方策を設けることが望ましいでしょう。当該指導者の関与禁止期間については悩ましいところですが、社会的に学校内におけるハラスメントに対して厳しい目線が向けられていることも踏まえれば、ハラスメント行為の軽重にかかわらず、期間を限定せずに関与を禁止することも十分考えられるところです。
また、部活動に関与する教職員や外部指導者等に対し、ハラスメント防止研修等を行うことも必要になると考えます。
◎部活動の外部指導者の行為に関する学校の使用者責任
法人など、自らの事業のために他人を使用する者は、その事業に関する活動をする中で、使用する他人が第三者に加えた損害について責任を負います(民法715 条)。ここでいう「使用」とは、必ずしも雇用契約を締結している場合に限りません。
部活動は学校教育の一環として行われる活動であることから、学校は、部活動の実施のために外部指導員を「使用する者」に該当します。裁判例の中にも、学校と雇用関係のない外部コーチによる部活動指導中に生じた事故に係る損害について、学校に対し、外部コーチの使用者としての賠償責任を負わせたものがあります(東京地裁平成29 年5月31 日)。
このように、学校は部活動中の外部指導者の行為について責任を負う立場にありますから、雇用関係にないといえども、外部指導者に対し、必要に応じた安全教育、ハラスメント防止教育等を行い、正常な部活動の運営が行われるよう適宜監督することが必要です。
この記事の内容は、『学校運営の法務Q&A』(旬報社)をもとにお届けしました。教育現場のトラブル回避や法的対応をサポートする信頼の一冊。全国の書店やオンラインストアでお求めいただけます!
こちらからもお買い求めいただけます。